私たちは、ファシリテーションや
サイエンスコミュニケーションのテクニックを活用し、
市民と科学技術との仲介者を務め、
市民の「わかる」と「知る」を
お手伝いする活動を実施します。
現在は、市民防災に関する事業と、
科学コミュニケーションに関する事業の
2つを主に実施しています。
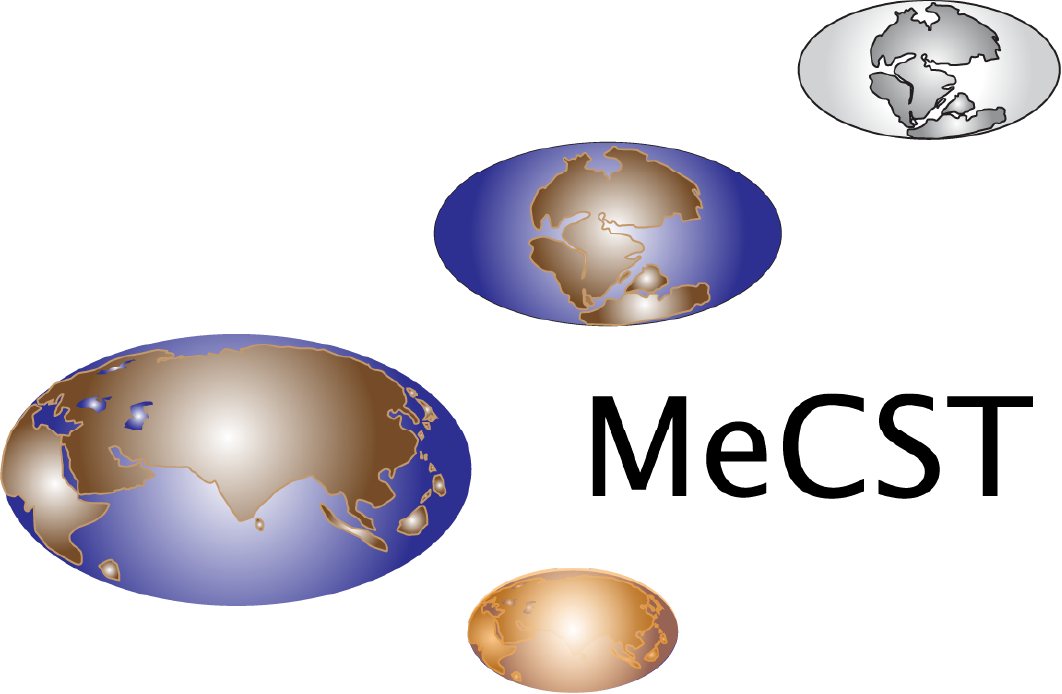
モットー
- 私たちは、市民が科学技術を良く知り、正しく恐れる活動に関わります。
- 私たちは、科学技術問題を扱う場の仲介者として、企画と進行をお世話します。
- 私たちは、予め答えが決まっている場には関わりません。
- 私たちは、何らかの答えを誘導するような行為には関わりません。
活動の概要
2023.10.2
【オスコイ通信 神恵内対話の場から 第6号発行のお知らせ】当会では北海道神恵内村における高レベル放射性廃棄物に関する対話の場について、運営をお手伝いさせていただいております、 参加者してくださっている方のお気持ちなどをお知らせする「オスコイ通信」第6号がまとまりました。「対話の場」に参加してくださっている方の生の声を、これからもお伝えできればと思います。 ファイルはこの記事をクリックするとダウンロードできます。
2023.6.3
【オスコイ通信 神恵内対話の場から 第5号発行のお知らせ】当会では北海道神恵内村における高レベル放射性廃棄物に関する対話の場について、運営をお手伝いさせていただいております、 参加者してくださっている方のお気持ちなどをお知らせする「オスコイ通信」第5号がまとまりました。「対話の場」に参加してくださっている方の生の声を、これからもお伝えできればと思います。 ファイルはこの記事をクリックするとダウンロードできます。
2023.4.5
当会副代表理事成田真由美による、「福島第一原子力発電所視察のご報告」をアップしました。
2022.9.23
2022年9月23日 令和3年度の貸借対照表について内閣府NPOホームページにおいて広告しました
2022.9.23
2022年8月1日 当会では北海道神恵内村における高レベル放射性廃棄物に関する対話の場について、運営をお手伝いさせていただいております、 参加者してくださっている方のお気持ちなどをお知らせする「オスコイ通信」第3号がまとまりました。「対話の場」に参加してくださっている方の生の声を、これからもお伝えできればと思います。
2022.9.23
2022年5月29日 北海道神恵内村で開催された「高レベル放射性廃棄物の最終処分に関するシンポジウム」のファシリテーターを当会代表理事大浦宏照が務めさせていただきました。
シリーズ「とことん聞いてみる」
アーカイブ
このところ、科学や技術が厄介です。
情報がたくさんあって、どれが正しいのかわからないし、聞けば聞くほど不安が増したりします。
少しでもみんなが「わかる」ように、幅広い疑問や意見や気持ちを取り扱えるような
「とことん聞いてみる」場を作りたいと思います。
その後、「対話」が進むことを祈って。
組織概要
- 概要
-
団体名 特定非営利活動法人
市民と科学技術の仲介者たち所在地 北海道札幌市 設立 2020年3月13日 代表理事 大浦宏照
- 私たちの理念
-
科学技術が発達し、生活が便利になりました。その一方で、市民は多くのリスクも保有しています。日本では水俣病などの公害病が発生し、原子力発電所の事故では、たくさんの放射性物質が生活環境に放出されました。そして、これからも新しい科学技術が表れ、新たなリスクも生じます。市民には科学技術の利点やリスクを知る権利があります。さらに、科学技術の専門家は、それらをわかりやすく市民に説明する責任があります。
「わかる」とは、「物事の意味・価値などが理解できること」です。科学技術は日々進歩し、原理や仕組みが複雑でわかりにくくなっています。専門知識のない市民が「わかる」には、「わかりやすさ」に配慮してデザインされた場が必要です。一方で「知る」とは、「物事の存在・発生などを確かにそうだと認める。認識する。」ことです。原理や仕組みがわかっても、それを市民が受け入れ「知る」には、「気持ち」に配慮したプロセスが必要です。そのため、私たちは、ファシリテーションやサイエンスコミュニケーションのテクニックを活用し、市民の「わかる」と「知る」をお手伝いします。
この活動を継続的に実施するには、他の団体や法人との協働が必須であり、それには社会的地位が明確な組織が必要です。また活動の中立性・透明性を確保するには、多くの市民が参画できる非営利団体であることが求められます。このような理由から、特定非営利活動法人格を取得することが最適であると考えました。
私たちは、幅広い世代の市民の「わかる」と「知る」をサポートし、科学技術に関する対話の場の、担い手の育成・デザイン及び伝え方の啓発・企画及び運営を通じ、保健・医療又は福祉の増進、社会教育の推進、まちづくりの推進、学術・文化・芸術又はスポーツの振興、環境の保全、災害救援、国際協力、子どもの健全育成、情報化社会の発展、科学技術の振興、経済活動の活性化を図ることを目的とします。
- 設立経緯
-
2019年9月17日 任意団体 市民と科学技術の仲介者たち 設立 2020年1月5日 設立総会開催 2020年3月9日 設立認証 2020年3月13日 登記完了
特定非営利活動法人 市民と科学技術の仲介者たち 設立
- 事業概要
-
当会は以下の事業を行っています。
- ①科学技術に関する対話の場の担い手育成事業
- ②科学技術に関する対話の場のデザイン及び伝え方の啓発事業
- ③科学技術に関する対話の場の企画及び運営事業
- ④その他この法人の目的を達成するために必要とする事業
- 決算公告
- 貸借対照表
